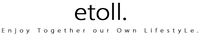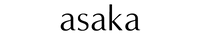様々な書類の郵送や宅配便を使うほどでもないサイズの商品を送るとき、封筒は何かと使う機会がありますよね。
ですが、封筒にはA4やB5といったサイズの表記がされていなくて、間違ってサイズが違う封筒を選んでしまうことがあります。
封筒のサイズは料金などが異なってしまうので選ぶときには注意が必要です。
そこで今回はそんな定形郵便と定形外との違い、様々な種類の封筒サイズ、定形郵便料金の解説や用途に適した封筒サイズの選び方を紹介します。
これから送る郵便物はどれが適しているのか確認してみましょう。
1.定形郵便と定形外郵便の違いやサイズについて解説
封筒のサイズは大きく分けて【定形】と【定形外】に分けることができます。
この二つの種類は郵便物の重量・サイズによって決められます。
これから送る郵便物は定形郵便になるのか封筒のサイズを確認してみましょう。
定形郵便
最小定形郵便物

最大定形郵便物

縦(長さ) |
14~23.5cm |
横(幅) |
9~12cm |
厚さ |
最大1cm |
重量 |
50g以内 |
上記のサイズや重さの郵便物はすべて提携が郵便物になります。
定形外郵便は重量1kg以内だと【規格内】で、重量1kg以上4kg以内だと【規格外】となります。
それぞれ幅や厚みといったサイズによって決められています。
定形外郵便
規格内の最大定形外郵便

規格外の最大定形外郵便

規格内の定形外郵便(重量1kg以内)
縦(長さ) |
14~34cm |
横(幅) |
9~25cm |
厚さ |
最大3cm |
規格外の定形外郵便(重量1~4kg以内)
A(縦)・C(横)・B(厚さ)の合計が90cm以内でA(縦)が60cm以内であること
封筒のサイズが定形郵便の最小サイズよりも小さい場合、定形郵便として扱われますので勘違いしないようにしましょう。
その為、封筒を使って郵送をする際は注意が必要になります。
2.種類ごとによる封筒のサイズについて
封筒の寸法規格は、JIS(日本工業規格)によって定められています。
形は【長形(ながかた)】、【角形(かくがた)】、【洋形(ようがた)】の3つに分別され、様々な使い方に適したサイズがあります。
種類ごとの特徴と一般的な封筒のサイズを紹介します。
長形

書類などを縦長に封入できる封筒は長形と言います。
縦書きの書類などと相性が良く、和封筒と呼ばれたりもします。
定形で送れるサイズが多いのでよく使用されます。
長形のサイズと用途について
| 名称 | サイズ(mm) | 定形/定形外 | 用途 |
| 長形1号 | 142×332 | 定形 | B4用紙三つ折り |
| 長形2号 | 119×277 | 定形 | B5用紙二つ折り・A4用紙二つ折り |
| 長形3号 | 120×235 | 定形 | A4用紙三つ折り・B5用紙二つ折り |
| 長形4号 | 90×205 | 定形 | B5用紙三つ折りまたは四つ折り |
| 長形5号 | 90×185 | 定形 | B5用紙三つ折り |
| 長形40号 | 90×225 | 定形 | A4用紙四つ折り |
| 長形30号 | 90×235 | 定形 | A5用紙二つ折り・B5用紙三つ折り |
この中でA4用紙を三つ折りで入れれる長形3号(ながさん)やB5用紙を三つ折りで入れれる長形4号(ながよん)はビジネスシーンで多用されます。
角形

長形封筒と比べて横幅が広くなったものが角形封筒です。
A4やA5といったサイズの用紙を折りたたまずに封入することができます。
サイズが大きくきれいに封入できますが、ほとんどが定形外郵便扱いになりますので気を付けてください。
角形のサイズや用途について
| 名称 | サイズ(mm) | 定形/定形外 | 用途 |
| 角形0号 | 287×382 | 定形外 | A4またはB4用紙は折りなし |
| 角形1号 | 270×382 | 定形外 | A4またはB4用紙は折りなし |
| 角形2号 | 240×332 | 定形外 | A4またはB4用紙は折りなし |
| 角形3号 | 216×277 | 定形外 | B5用紙は折りなし |
| 角形4号 | 197×267 | 定形外 | B5用紙は折りなし |
| 角形5号 | 190×240 | 定形外 | A5用紙は折りなし |
| 角形6号 | 162×229 | 定形外 | A5用紙は折りなし |
| 角形7号 | 142×205 | 定形外 | B6用紙は折りなし |
| 角形8号 | 119×197 | 定形 | B5用紙三つ折り |
A4サイズをきれいに入れられる角形2号(かくに)は履歴書や契約書などの書類のほかにもパンフレットなどを入れるときにも使えます。
洋形

中身を横長にして封入するタイプの封筒です。
二つ折りをした紙の両端を貼り合わせる【カマス貼りタイプ】とフタが三角形になっている【ダイヤモンド貼り(ダイヤ貼り)タイプ】の2つのタイプに分けられます。
よく便せんやメッセージカードを封入するときによく使われます。ほとんどのサイズが定形郵便で郵送することができます。
洋形のサイズと用途について
| 名称 | サイズ(mm) | 定形/定形外 | 用途 |
| 洋形0号 | 235×120 | 定形 | A4用紙三つ折り |
| 洋形1号 | 176×120 | 定形 | A5用紙三つ折り・招待状・カード |
| 洋形2号 | 162×114 | 定形 | A5用紙二つ折り・はがき |
| 洋形3号 | 148×98 | 定形 | B5用紙十字折り |
| 洋形4号 | 235×105 | 定形 | B4用紙三つ折り |
| 洋形5号 | 217×95 | 定形 | A5用紙二つ折り |
| 洋形6号 | 190×98 | 定形 | B5用紙三つ折り |
| 洋形7号 | 165×92 | 定形 | A5用紙三つ折り |
これら以外にも洋形長3号(120×235)・洋形長4号(90×205)・洋形特1号(138×198)といった種類があります。
洋形特1号のみ定形外なので郵送に使う際は気を付けてください。
3.用途に適した封筒の選び方や定形郵便料金の紹介

最後に用途に適した封筒のサイズの選び方と定形郵便料金と定形外郵便料金を紹介します。
これから使う封筒が最適な封筒なのか、郵便料金は高くならないか確認しておきましょう。
用途に適した封筒サイズの選び方
封筒のサイズは郵便料金やキレイに封入するための大切なポイントになります。
ビジネスシーンではA4サイズの用紙を三つ折りで入れれる長形3号が最も使用されます。
折り曲げたくない大事な書類やカタログ・パンフレットを郵送する場合は大き目の角形封筒を選ぶ必要があります。
小さめの案内状や招待状、便せん・メッセージカード、DM(ダイレクトメール)の場合は洋形封筒がオススメです。
ですが、封筒を選ぶときには受け取り手のことを考えてサイズを選ぶことも大切な要素になります。
招待状など封筒に入れたまま持ち運びする場合は持ち運びしやすいサイズを選ぶ必要があります。
封筒のサイズが無いからといって、折り目がたくさんついた書類が小さい封筒に入っていたら受け取り手はもやっとした気分になってしまいます。
内容物のサイズや容量以外にも折っても大丈夫な書類なのか受け取りての気持ちや郵送するシーンを踏まえてサイズを考えることが大切です。
定形郵便料金と定形外郵便料金の紹介
郵送をする際は定形・定形外・サイズに関わらず重量で切手代(郵送料金)が決まります。
原則として重量が重いほど料金が高く、軽ければ安くなると覚えておきましょう。
定形郵便料金
| 25g以内 | 84円 |
| 50g以内 | 94円 |
定形外郵便料金
| 重量 | 規格内 | 規格外 |
| 50g以内 | 120円 | 200円 |
| 100g以内 | 140円 | 220円 |
| 150g以内 | 210円 | 300円 |
| 250g以内 | 250円 | 350円 |
| 500g以内 | 390円 | 510円 |
| 1kg以内 | 580円 | 710円 |
| 2kg以内 | 取り扱い無し | 1,040円 |
| 4kg以内 | 取り扱い無し | 1,350円 |
一度に大量の郵便物や荷物を送る際は郵便料金が割り引かれることもあります。
※記載している金額は2024年2月時点の価格となっており、価格改定が行われている可能性がありますので注意してください。
おわりに
ここまで紹介してきたように封筒には様々なタイプとサイズがあります。
今回ここまで紹介してきた封筒のサイズや用途・料金を押さえ綺麗に安く書類を送れると思います。
これから郵送する予定の書類や荷物は安くきれいに送れるようにしておきましょう。
封筒のサイズや郵便料金の変化がよくわからないとお悩みの人はぜひ参考にしてみてください。
似た記事を探す
MEDIA