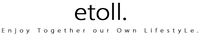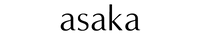3月3日には桃の節句のひな祭りがありますね。
日本の伝統的な文化でひなあられを食べたり、ひな人形を飾ったりする女の子のイベントといったざっくりとした情報は知っていますが詳しいひな祭りの由来や意味を知っている人は少ないと思います。
今回はそんなひな祭りとはどんな行事なのかといった由来や意味について詳しく解説をしていきます。
ひな祭りの理解を深めて子どもたちにも伝えれるようにしておきましょう!
1.ひな祭りとは?意味や由来について
まず最初にひな祭りを行う意味や由来を解説していきます。
ひな祭りをお祝いするための理解を深めましょう。
ひな祭りについて
ひな祭りの風習について
3月3日に行われるひな祭りは女の子が健やかな成長や幸せを祈ってお祝いをします。
幸せでいれるように願いをこめてひな人形を飾ることが現代のひな祭りの風習となっています。
ひな祭りには人形を飾るだけでなく、花を供えてお菓子や食事をしたりします。
ひな人形を飾るのには女性を難事から守るといった意味合いも込められています。
ひな祭りの由来について
ひな祭りの由来は平安時代中頃に紙人形を作って川や海にその人形を流し、身のけがれをお祓いする行事から来ているとされています。
現在でも、一部の地域でこの【流し雛(ながしびな)】の風習が残っており、行われます。
【ひな】の語源について
和歌山市加太には、ひな人形の供養で有名な淡嶋神社があり、ご祭神として少彦名命(すくなひこなのみこと)が祀られており、女性の病気回復や安産にご利益があるとされています。
この【すくなひこな】の【ひこな】が転じて、【ひな】の語源となったともいわれています。
また、平安時代に女の子が遊ぶ人形を【ひいな】と呼んでいたことから、この【ひいな】が時代とともに変わっていき【ひな】となったともされるといった諸説あります。
ひな人形の歴史について
ひな祭りのシンボルであるひな人形には願いやお払いの為にあるのはわかりましたが、どのようにして私たちの生活に浸透したのでしょうか。
ここではそんなひな人形の歴史について紹介します。
ひな人形の起源
ひな人形は中国にある【上巳節】という3月の節句と災難や厄を人の代わりに受けてくれる人形を川へ流す【流しびな】という行事に平安時代に行われていた人形遊び【ひいな遊び】といった様々な行事が合わさった生まれたとされています。
【上巳節】という春へと移り変わる季節の節目に悪いことが起こらないようにという思いで厄払いを行っていたものが日本へと伝わり、【流し雛(ながしびな)】と【ひいな遊び】が時代とともにひな人形で女の子の幸せを願うひな祭りという行事に変わっていったとされています。
流しびなは江戸時代の江戸幕府によって5つの節句が制定されます。
5月5日の端午の節句(こどもの日)には男の子の成長を祝い、3月3日の桃の節句(ひな祭り)には女の子の成長を祝うようになります。
この時代は職人の手により人形作りの技術も上がり、非常に美しく価値のある物に変わっていきます。
そんな綺麗な人形は川に流されなくなり、家の中で大切に飾る物に変わることになりました。
豪華なひな人形は武士の家に嫁ぐ際の嫁入り道具の一つとしても加えられ、高価なひな人形を持つことは家の裕福さのアピールとなり、他にも大きなひな壇も加わり、現在のひな人形に変わっていきます。
お内裏様(おだいりさま)とお雛様(おひなさま)の並べ方について
ひな人形にはお雛様とお内裏様は【お雛様を女雛】、【お内裏様を男雛】と呼ぶこともあります。
お内裏様の【内裏】ですが、宮殿(天皇さまの私的区域)のことを指し、本来は【お殿様】と呼ぶのが正しい、とも言われています。
現代では向かって左にお内裏様を右にお雛様を並べていましたが、昔は逆に並べていました。
この逆に並べるのは京都などの一部地域では現在でも並べられています。
並べ方は昭和天皇の即位大礼があり、天皇が向かって左に皇后が向かって右に並び、写真撮影をしたためになります。
この出来事をきっかけに様々なメーカーが並び方を変えるきっかけになり現在の並び方になりました。
この、向かって左に男性が右側に女性を並ぶことを西洋式の並び方とされています。
桃の節句と呼ばれる理由
桃の花は日本でも古くから親しまれており、もともとは中国を原産とする植物です。
中国では桃の実には魔除けや邪気を払う力があるとされており、日本でも縁起の良い植物とされています。
百歳(ひゃくさい)を【ももとせ】とも呼ぶことから長寿の象徴でもありました。
旧暦の3月初旬は桃の花が見ごろだったこともありひな祭りを【桃の節句】として桃の花が飾られるようになりました。
桃の花は春の季語でもあり、ひな祭りにぴったりの花になっています。
2.ひな人形はいつからいつまで飾るの?ひな人形のバリエーションの紹介
ひな人形はいつ飾り、いつ片づけるのでしょうか?
ひな人形を飾るタイミングと片づけるタイミングはちゃんとありますので飾ったり片づけたりする前に確認しておきましょう。
ひな人形の飾りはじめ
飾りはじめは1月中旬~2月中にしましょう。
飾りはじめには地域により差がありますので、悩んだ際は上記の期間内に飾ればいいでしょう。
ひな祭りと縁のある京都では節分の後の2月4日ごろからひな人形を飾り始めます。節分で厄を払った翌日にひな人形を出す流れになります。
他には2月18日・19日あたりの二十四節気の雨水(うすい)の時期に出すといい説もあります。
雨水は農耕の準備を始める目安でもあり、水で厄を流してきた上巳の節句らしい考え方とされており、雨水に人形を飾り始めると良縁に恵まれるという言い伝えが一部の地域に残っています。
東海の一部の地域では1月8日ごろから飾り始めたりもします。
片付けの時期について
片付けは3月4日~4月中旬の晴れの日にしましょう。
ひな祭りが終わりましたら湿気の少ない晴れの日にしまいましょう。
ひな祭りは4月3日の旧暦で祝う家もある為、片付けの猶予が広くなっています。
旧暦でひな祭りを祝う際は3月5日の啓蟄(けいちつ)に片づけるのがオススメです。
片付けが遅れると婚期が遅れるという迷信があります。
これは人形に代わってもらった役が戻ってくる考えがある為、早く片付けて休んでもらう必要があります。
その為ひな人形の片づけはできる限り早くやりましょう。
ひな人形の種類について
江戸時代前期までは紙でひな人形が作られていました。
この紙で作られたひなは紙立雛(かみだちひな)と呼ばれています。
ですが現在は大勢の侍従や飾りに囲まれた華やかなひな人形をよく見ますよね。
ではそんな華やかなひな人形にはどんな種類があるのか紹介します。
| 配置 | 京雛・関東雛 |
| 人数 | 親玉飾り・五人飾り(二~三段飾り)・七段飾り |
| 素材 | 紙・木・土(陶磁器)・布 |
| 衣装 | 衣装着人形・木目込み人形 |
| ケース | 収納飾り・ケース飾り・段飾り |
上記の飾り方は家で飾るときですが、他には流し雛や吊るし雛もあります。

3.ひな祭りを味わおう!ひな祭りに食べたい食べ物の紹介
ひな祭りを祝う際にはどんな食べ物を用意すればいいのでしょうか?
縁起がいい食べ物や色鮮やかで見て楽しめる食べ物ばかりなのでぜひ用意してみてくださいね。
菱餅(ひしもち)
水面に広がって繁る植物の菱(ひし)に由来しています。
ひし形は昔から成長や繁栄のシンボルとして親しまれてきました。
| 桃色 |
魔除け |
| 白色 |
清浄 |
| 緑色 | 健康 |
諸説ありますが、ひし餅の色には意味が込められており、どれも女の子の健やかな成長と豊かな人生を願う意味が込められています。
鮮やかな色を楽しみながら食べましょう。
ひなあられ
ひなあられもひな祭りには欠かせない食べ物ですよね。
ひなあられはひし餅を外でも食べやすくするために砕いて焼いたのが発祥と言われています。
ひなあられは関東では甘いポン菓子で関西は塩味のおかきが主流になり桃色ます。
| 桃色 |
生命 |
| 白色 |
雪の大地 |
| 緑色 |
木々の芽吹き |
諸説ありますが、ひなあられにの色にも意味があり、3色の自然のエネルギーを得て元気で丈夫に育つとされています。
4色のひなあられもあり、四季を表していると言われています。
ひなあられを食べてひな祭りを楽しみましょう。
ハマグリのお吸い物
蛤(はまぐり)は同じ個体の殻同士でないと合わないことから、良い結婚や良縁の象徴になっています。その為、結婚式やひな祭りで食べる風習があります。
ハマグリの旬は2月~4月頃ですのでひな祭りの時期にもぴったりです。また、ちらし寿司とも相性がいいのでぜひちらし寿司と一緒に蛤のお吸い物を食べてみてください。
ちらし寿司
お寿司の起源とされている【なれ寿司】にエビや菜の花などを乗せて彩をよくして食べたのが由来とされています。
具材にも子供の健康や成長を願う意味が付いています。
| エビ |
長生きできますように |
| レンコン |
先が見通せるように |
| 豆 | 健康でマメに働けるように |
ピザやケーキ
最近ではひな祭り仕様のケーキも多くあります。
手軽にお祝いすることができ、子供たちにも人気なメニューです。
ピザを選ぶときもひな祭りに通じるチーズの白色、エビの桃色、ブロッコリーの緑色といった具材が入ってるとよりひな祭りを演出できます。
また、ひな祭りの時にはピザのキャンペーンがやっていたりするのでピザを用意する際はチェックしておきましょう。
4.ひな祭りは英語でなんと言う?
代表的な日本文化の一つであるひな祭りは海外でも認知がされてきています。
海外から来られた人たちに読み書きをして伝えれるようにチェックしておきましょう。
ひな祭りの英語の言い方
ひな祭り
Hinamatsuri
Doll’s Day
Girl’s day
ひな祭りは日本の文化の為、英語で言う場合もHinamatsuriになります。
ひな祭りにはひな人形を飾るので、人形という意味を持つDollが使われています。
また、ひな祭りは女の子を祝うので、女の子を意味するGirlが使われていますが最近ではジェンダー問題もあるので、最後のGirl’ dayは避けたほうがいいかもしれません。
ひな祭りは桃の節句とも言いますが【桃の節句=Girl’ day】となります。
ひな人形の英語の言い方
お雛様(おひなさま)
Hina-Dolls
ひな祭りと同じく、日本の文化ですのでそのままローマ字で表記し、言いましょう。
ですが、海外の人たちはHina-Dollsと言っても伝わらないので下記の例文のように伝えましょう。
例文:It is a doll displayed during the Hinamatsuri.
和訳:ひな人形はひな祭りで飾られる人形のことです。
雛人形(ひな人形)
Hina-ningyo
こちらも先ほどと同じく日本の文化ですのでそのままローマ字で言いましょう。
先ほど説明したお雛様と雛人形は同じ意味でもあるのでHina-Dollsと言っても大丈夫です。
Hina-ningyoと説明する際はningyoが伝わらない為、下記の例文を使い説明しましょう。
例文:Ningyo means Dolls in Japanese.
和訳:Dollは日本語で「人形」と読みます。
さいごに
ひな祭りは長い歴史のある日本文化ですので、子供たちとひな祭りの歴史を学んだり、ひな祭りの料理を楽しんでみてください。
ぜひお雛様を飾っておいしい料理をたくさん用意して家族みんなでひな祭りを楽しみましょう。
似た記事を探す
MEDIA